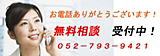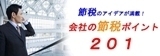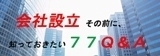粗利益率とリスクの関係を知る 2009.07.31
「粗利益率の高い商売を選択する」の重要性を理解するためには、その逆である「粗利益率の低い商売」の恐ろしさを知るのが一番だ。
粗利益(あらりえき)は、会計上、「売上総利益」と言い、損益計算書の上の方に表示されている。しかし、粗利益の方が一般的な名称なので、今回はこちらを使用する。
まずは「粗利益」と「粗利益率」を導く公式を理解しよう。その上で設問を解いていただきたい。なお、ここでは話をシンプルにするために、仕入以外の売上原価は発生しないものとする。また、在庫を持たず、仕入れた直後に販売するものとする。
● 売上高 − 仕入高 = 粗利益
● 粗利益 ÷ 売上高 = 粗利益率
問1.粗利益と粗利益率を求めなさい
例① 90万円で仕入れた商品を100万円で販売するケース
100万円(売上高)―90万円(仕入高)=10万円(粗利益)
10万円(粗利益)÷100万円(売上高)=10%(粗利益率)
→ この後は「粗利益率10%の商売」と呼ぶ
例② 10万円で仕入れた商品を100万円で販売する
100万円(売上高)―10万円(仕入高)=90万円(粗利益)
90万円(粗利益)÷100万円(売上高)=90%(粗利益率)
→ この後は「粗利益率90%の商売」と呼ぶ
※粗利益率10%の商売と、粗利益率90%を比較すると、粗利益と粗利益率がそれぞれ9倍違うことがわかる。
問2.売上先が倒産した場合の実質損害額を求めなさい
例① 粗利益率10%の商売
収入はゼロだが、仕入先に90万円の返済義務が発生する。
例② 粗利益率90%の商売 収入はゼロだが、仕入先に10万円の返済義務が発生する。
※粗利益率10%の商売と、粗利益率90%の商売を比較すると、損害額が9倍違うことがわかる。
問3.利益に対するリスク(損害額)の大きさを求めなさい
例① 粗利益率10%の商売 問1①で求めた10万円の利益を得るためには、問2①で求めた90万円の損害を負う。つまり利益に対して9倍のリスクを負う。
例② 粗利益率90%の商売
問1②で求めた90万円の利益を得るためには、問2②で求めた10万円の損害を負う。つまり利益の9分の1のリスクを負う。
※粗利益率10%の商売と、粗利益率90%の商売を比較すると、利益に対するリスクの割合は、それぞれ9倍と9分の1倍になり、実に81倍もの違いが発生する。つまり、粗利益率が9分の1だと、同じ利益を得るためには、81倍ものリスクを負わなければならないことになる。
好況時はリスクの発生率がもともと低いため、81倍あったとしても、実害が発生する可能性はほとんどない。しかし不況時には、この差が顕著に表れる。この事実に気づけば、不況時に粗利益率の低い商売を選択することが、いかに恐ろしいのかがわかると思う。